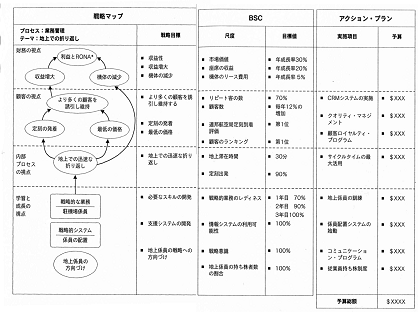サービスデザインとデジタルトランスフォーメーション(SDGC2018参加報告)
SDGC2018 Discover to Deliver

今年のService Design Global Conference(SDGC)は、10/10~10/12にダブリンで開催されました。
今年のテーマは、
Discover to Deliver
でした。
左図は有名なサービスデザインのプロセスを示すダブル・ダイアモンドですが、今年は特にDeliverに焦点があたった内容となっていました。
さらに付け加えるならば、Deliverの中のImplementation(実装)を強く意識した内容となっていました。
Implementationには二つの要素があります。
ひとつは昨年度からのテーマである、組織への浸透=組織文化への変革です。
もうひとつが、デジタル化への対応です。
IT側からのアプローチでは、必ずと言っていいほどなおざりにされるのが、一つ目の課題です。
このブログのBSCのテーマでも述べてきましたように、情報資本の整備だけでは不十分で、人的資本、組織資本のレディネスも同時に高めないと、戦略は実現できません。
サービスデザインはCo-Creationを基本としているので、人的資本、組織資本のレディネスを高めているといえます。
一方、サービスデザインはデザイン系の方が中心となって発展してきたので、「デジタル化への対応」という点で、特に最近の著しい技術進歩への対応について懸念があります。AI、IoT、OpenData、Cloudなどを活用できないと、新しい顧客経験をデザインできない状況になってきています。
デジタルトランスフォーメーションのテーマで述べてきたように、「急速にデジタル化が進む」という認識が広く一般的になってきていることの証左だと考えられます。
デジタルトランスフォーメションの目的は、「新たな顧客経験を提供することである」ということは以前にも記述しました。顧客経験をデザインする手法であるサービスデザインは、この目的に適合するものでありますが、「KAIZEN」の枠組みから出れないというリスクもはらんでいます。
顧客起点にたって、潜在するペインポイント(MITのデザイン思考ではLatent Needsと表現しています)をしっかりと認識できていれば、KAIZENに留まることはないのですが、なかなか供給者視点が抜け切れないことが多く、このため考案された新たなしくみに「素晴らしい経験」というレベルに達しないものが多くなります。
この点は、IT系のプロジェクトとも深く共通するところがあります。
今回のカンファレンスでは、「全く新たな顧客経験をデザインする」ために、AI、IoT、OpenData、Cloudをいかにうまく活用するかという観点からのプレゼンやワークショップが多くみられました。
今年のIRCE2018でも同様のプレゼンがあったのですが、デジタル化が急速に進むため、「今日のNewは明日には当たり前になってしまう」ということがやはりプレゼンされていました。
このため、ワークショップや講演では、デザイン系の人にAIとは何か、IoTとは何かを丁寧に説明していました。
(自分の大学院での講義のレジュメを見ているようで、面白かったです)
欧米の参加者とも会話しましたが、デジタルトランスフォーメーションが進んできているので、サービスデザインにおいても、デジタルを前提として考えざるを得ない状況になっているということを共通に語っていました。
このような背景から、今年のAwardも昨年度までと比べて、「デジタル」の要素を強く含んだケースが受賞していました。
米国の地方警察のデジタル化事例もその一つでしたが、事例の紹介はまたの機会にします。
デジタルトランスフォーメーションのEA設計の鍵 ペースレイヤーモデル
ペースレイヤーモデルの概念がガートナーから提唱されたのは2012年です。
https://www.gartner.com/newsroom/id/1923014
当時はアジャイル開発対ウォーターフォールという不毛な議論が盛んな時代でしたが、Pace Layered Modelを適用することにより、明確な役割分担の指針を出すことができると考えました。
その後、同じくSystem of Recordsという概念を有するバイモーダルITのコンセプトが広まったために、Pace Layered Modelはあまり広まりませんでした。
しかしながら、デジタルトランスフォーメーションの時代になって、戦略との整合性をも設計できるPace Layered Modelを改めて使う時がきたと考えています。
それを的確に表したのが、2016年4月にガートナーが公開した「Pace-Layered Application Strategy and IT Organizational Design」に掲載された下記の図です。

ベースとなる座席管理のサブシステムは、Systems of Recordと分類され、しっかりと確実に作られるべきだとしています。この部分は近いうちにブロックチェーンに置き換わるかもしれません。一方、料金体系は戦略に応じて様々なものが設定されるため、料金エンジンは差別化のためのシステムとして分類されています。戦略との整合が最も強く現れるところです。
ここの更新頻度は半年に一度位でしょう。ホテルの宿泊料金に様に需要予測から設定する変動型にしておくと一年に一度位の変更で済むかもしれませんが、ユーザーに不安感を与えるので、ある程度は予測可能なモデルにしてくべきでしょう。このようなルールの考え方がすなわち会社戦略を反映しているわけです。
一方エンドユーザーと接するSNS連携やWebアプリ(スマホアプリでも同じです)の部分は革新システムとして位置づけられています。
差別化システムについては明確な差別化戦略がありそれに基づいて構築されます(またはそうあるべきです)が、革新システムは予測がつかないものであり、不毛な机上の空論で時間を費やすよりも、早く市場に投入し、その反応を見ながらスパイラル型でブラッシュアップしていくスタイルが必要となります。もしくはそのスタイルを取らなければ、誰にも使ってもらえないアプリになります。
このようにデジタルトランスフォーメーションの時代のシステムは、3つの異なる性格を持つシステムで構築されることになります。バイモーダルITのモデルではこの部分がうまく説明できないのです。
さて、上記の図に示したような美しいアーキテクチャを採用できるようになるには、企業システム全体がある程度成熟している必要があります。縦割りの部分最適な状態では上記のアーキテクチャを採用したシステムが稼働できないからです。
ということで、次回からはEAの発展段階を整理するフレームワークとして「アーキテクチャ成熟度ステージ」をご紹介します。
デジタルトランスフォーメーションとエンタープライズアーキテクチャ
前回まで企業戦略とIT投資の整合を図る方法として、BSCと情報資本ポートフォリオについてお話をしてきました。
情報資本ポートフォリオを使ったマネジメントの基本的な考え方は、企業の戦略との関係性において自らが保有する情報資本のレディネスを高めるということでした。
エンタープライズアーキテクチャは、企業の保有する情報資本すべてをマネージメントするための考え方で、全体最適を進めるにあたっては、必要不可欠なフレームワークです。
エンタープライズアーキテクチャ(EA)の基本的なフレームワークは、下記の図に示すように、企業の持つ情報資本を、BA、DA、AA、TAの4層に分けて可視化しマネジメントしようとするもので、情報資本ポートフォリオも実はこのEAのフレームワークと同じ構造をしています。(内部プロセスの視点がBAに相当します)

出典:ITアソシエイト協議会「業務・システム最適化計画について(Ver.1.1)~ Enterprise Architecture策定ガイドライン~」平成15年12月
情報資本ポートフォリオは戦略と関係の深い情報資本のみにフォーカスを充てています。そのため、情報資本ポートフォリオにはすべての情報資本が掲載されているわけではわりません。逆にいうと、EAが整備されていると、情報資本ポートフォリオの作成が非常に容易になります。
一方、EAに掲載されている情報資本には、それがどのような技術で構築されているのかは記載されていません。メインフレームもクラサバも、Webベースも、クラウドもすべて同じアプリケーションとして記載されています。
しかしながら、デジタルトランスフォーメーションにおいては、テクノロジーレベルのアーキテクチャの設計が必要となります。
この検討のために、EAにガートナーのペースレイヤ―モデルを組み込んだフレームワークを利用します。

出典:https://www.slideshare.net/jeffshuey/pace-layered-approach-and-winshuttle-share-point-conference-nov-2012-jeff-shuey
次回は、このペースレイヤ―モデルの説明から始めます。
BSCによるIT投資マネジメントの要 情報資本レディネス
前回は情報資本ポートフォリオを使って、新しい業務プロセスのために必要となる情報資本を明らかにするフレームワークをご紹介しました。今回は、その次のステップとして、IT投資の内容を決定する方法を示します。
その際に利用するのが、下記の「情報資本レディネス」というフレームワークです。

出典:「戦略マップ」:ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、櫻井通晴・伊藤和憲・長谷川惠一監訳(ランダムハウス講談社,2005年)
情報資本ポートフォリオでは、新しいビジネスプロセス(左側バリューチェーンプロセス、右側バックオフィス)を実現するためにどのようなアプリケーションおよびそれを支えるITインフラが必要かを定義しましたが、情報レディネスの図の上段には各プロセスクラスターにおける戦略テーマが示されており、下段には各テーマに対する既存情報資本のレディネス評価の結果が示されています。
その結果をまごめると商品ラインのクロスセルという戦略テーマに対しては、進捗が遅れているPPMのプロジェクトにテコ入れをし、ICFとCRMに若干の機能強化をすれば良いということがわかります。
一般に企業では多くのシステムが既に稼働しているわけですから、新しい業務プロセスを実施するにあたって、既存のシステムの変更で対応できるのか、新しく構築するのが必要なのかなどを判断することは、極めて理にかなっていると考えることができます。
さて、新しい業務プロセスは情報資本への投資によってのみ実現できるものではありません。戦略人材の確保も同時に必要となります。下図はその検討のフレームワークを示したものです。この図では、顧客管理プロセスに関して「商品ラインのクロスセル」という戦略テーマが設定されており、その実現にあたって「フィナンシャル・プランナー」という戦略人材が必要であると定義され、人的資本にはその人材に求められる属性が示されています。

出典:「戦略マップ」:ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、櫻井通晴・伊藤和憲・長谷川惠一監訳(ランダムハウス講談社,2005年)
以上ご紹介したように、第3世代のBSCでは、合理的に戦略をアクションプランに展開することができます。
以前に櫻井教授らとともにキャプラン教授と対談した際に、「自分はもともとMITの出身なのでで、システマティックに整理することが好きなのだ」というようなことをおっしゃっておられました。確かに、BSCだけでなくABCも非常によく構造化され、実行しやすいものになっています。
BSCを戦略マネジメントツールとして活用できるためには、部分最適ではなく全体最適を目指す必要があります。一つは組織間の調整を如何に図るかというもの、そしてもう一つはエンタープライズ。アーキテクチャとの関連です。
次回からはエンタープライズ・アーキテクチャについて掘り下げていきます。
BSCによるIT投資マネジメントの要 情報資本ポートフォリオその2
前回簡単に情報資本ポートフォリオを説明しましたが、その活用方法の説明の前に、「戦略マップ」では、情報資本をどのように定義しているのかをまず説明します。

出典:戦略マップ」
ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、櫻井通晴・伊藤和憲・長谷川惠一監訳(ランダムハウス講談社,2005年)
上記はキャプランとノートンが定義している情報資本ですが、この定義はPeter WeillのITポートフォリオの考え方を引き継いだものです。一般に業務アプリケーションを業務(処理)系と情報系に分類しますが、この定義においても同様ですが、これらのアプリケーションの中で特に次の戦略との関係が深いものを「変革アプリケーション」として特だししています。どのアプリが他社よりも「卓越」しなければならないのかが、よくわかるようになっています。また、インフラにおいても「マネジメント・インフラ」が定義されているのは、要注意です。COBITのPOを見ると情報アーキテクチャや技術アーキテクチャの制定が情報戦略の重要な要素として位置づけられていますが、その思想がここにも反映しています。J-SOXにおいてIT全般統制に関して種々のドキュメントを整備させられましたが、それらもマネジメントインフラとして位置づけられています。EAが定着している欧米ならではの発想ですね。

出典:戦略マップ」
ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、櫻井通晴・伊藤和憲・長谷川惠一監訳(ランダムハウス講談社,2005年)
この情報資本をビジネスプロセス(正確にはビジネスクラスター)との関連を意識して整備したのが情報資本ポートフォリオです。図の左側は戦略実現に直接貢献するものであり、内部プロセスの視点の戦略目標を実現するために設計された新しいビジネスプロセスのために必要となるアプリケーションは何かが示されています。復習になりますが、企業の業務プロセスを大きく、イノベーション(商品開発)、顧客マネジメメント、オペレーションマネジメント(調達、生産、物流)の3つに分類し、それぞれにおいて必要なる変革アプリケーション、分析アプリケーション、トランザクション処理アプリケーションは何かを示しています。(ここはエンタープライズアーキテクトの腕のみせどころです)。
図の右側は間接的に戦略実現に貢献するもので、人的資本、組織資本に関わるアプリケーションが示されています。
そして、これらの新しいアプリケーションを稼働・開発・運用するために必要な物的インフラ。マネジメントインフラを図の下部において示します。
ところで、これらのアプリケーションやインフラは全て一から作るかというとそうではありません。企業には既に稼働しているたくさんのアプリケーションがあります。そこで、「レディネス」という概念が非常に重要になってきますが。これについては、次号で紹介します。
BSCによるIT投資マネジメントの要 情報資本ポートフォリオその1
情報資本ポートフォリオをご紹介する前に、IT投資マネジメント成熟度モデルというものをご紹介します。
IT投資マネジメントにおいて最もハードルが高いのは、個々のIT投資の評価ではなく、「全体最適=戦略との整合性を図ること」です。
そのため、IT投資マネジメントがどの程度うまくできているかどうかを判断するための物差しとしてIT投資マネジメント成熟度モデルというものがGAOから提示されています。

出典:GAO, "INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT MANAGEMENT A Framework for Assessing and Improving Process Maturity", March 2004 を宗平訳
IT投資の起案が上がる際に、個々についてその可否を判断しているというのがステージ2で、多くの企業がその段階にあるといえます。
成熟度モデルの基本として、まず目指すべきターゲットはステージ3になります。この内容をみると、事前評価、中間評価、事後評価というマネジメントプロセスだけでなく、IT投資ポートフォリオをベースとして全体最適を常に図ろうとしていることがわかります。
事前評価、中間評価、事後評価のプロセスを持つ企業は多いと思われますが、その判断がプロジェクト単位ではなく、全体最適、すなわちエンタープライズアーキテクチャと照らしあわせて行われている企業は非常に少ない様に思われます。
全体最適の視点を有するかどうかによって各評価における評価基準は大きく変わります。実は、ここに多くの企業が部分最適に陥っている理由があるのではないかと思っています。
ITポートフォリオの記載方法にはいくつか種類がありますが、戦略との連携を明確にするために、BSCの情報資本ポートフォリオを以下に紹介します。

出典:戦略マップ」
ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、櫻井通晴・伊藤和憲・長谷川惠一監訳(ランダムハウス講談社,2005年)
詳細は次号にて
BSCでIT投資/HR投資をマネジメントする 第3世代のBSC
前回第2世代のBSCで戦略マップのテンプレートが登場し、顧客の視点に示されている顧客への3つの価値提案、「卓越した業務」、「顧客関係重視」、「製品リーダーシップ」、これがすなわち企業がとりうる戦略になり、この戦略に応じて内部ビジネスプロセスにおいてどの部分を卓越させるのかを企業の成功のシナリオ仮説をデザインするということをご紹介しました。
しなしながら、戦略マップのテンプレートにおいて、改革の起点となる4つめの視点、学習と成長の視点については、今ひとつ何を決めればよいのかあいまいでした。
この疑問に答えるべく、まとめられた「戦略マップ」という本(第3世代のBSC)では、特に学習と成長に視点に関して「無形の資産」としてその整備を図るのであるということが明快に示されました。

出典:「戦略マップ」、ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、櫻井通晴・伊藤和憲・長谷川惠一監訳(ランダムハウス講談社,2005年)
無形の資産(インタンジブル・アセット)は人的資本、情報資本、組織資本から構成されるのですが、戦略との関係において「レディネス」という考え方が導入されています。これは戦略に対して準備ができているかどうかの状態を示すもので、顧客への新しい価値提案のために新しい業務プロセスを構築し稼働させる必要があるわけですが、それに必要な人材は揃っているのか、情報システムに過不足はないのか、会社の制度や組織文化は適合しているのかなどを評価していきます。
インタンジブルアセット、レディネスに加えて、下記に示すように戦略マップ・BSCの構造についても大きな変化がありました。
まず最初の変化は戦略マップ・BSCをプロセスクラスター毎に作成することになったことです。第2世代の戦略マップでもプロセスクラスターの概念は示されていたのですが、プロセスの軸を考慮せずに戦略マップを作成し、非常に分かりにくい=戦略マネジメントに失敗するというケースが多々でてきました。
そこで、第3世代では、まずはプロセスクラスター毎に戦略マップ・BSCを作成し、必要に応じて統合するというアプローチをとるようになりました。「戦略マップ」の本にはプロセスクラスター毎の戦略マップとKPIの例が詳細に提示されていますのでリファレンスとして使ってください。
プロセスクラスターをしっかりと意識することで、組織との関係性も明確になってきます。加えて、次回ご説明しますが、情報資本との関係も明確に定義ができるようになります。
次の変化は、事前指標、事後指標を定義しなくなったことです。財務の視点のパフォーマンスドライバーは入りについては顧客の視点、出るについては内部プロセスの視点になります。また上位組織の各指標のパフォーマンスドライバーは下位組織の指標になります。このように考えると各戦略目標について事前指標、事後指標を設定すると重複を生むことになり、実際には重複を避けるために無用に指標を増やすことになるだけだということで、戦略目標については成果指標を設定するのみとなりました。
最後の変更点はアクションプランの正式な設定です。これまでは戦略目標と施策との関係を明確にしていなかったために、戦略は立案したものの実行されないということも起きていました。そこで各戦略目標についての施策をアクションプランとして設定し、その予算を戦略予算として管理することとしました。
ここで注意すべきは財務の視点のアクションプランは設定してはいけないということです。その理由については、次回までの皆さんの宿題とします。
次回は情報資本ポートフォリオを使ったIT投資マネジメントについて解説します。
BSCを使えるようになる 戦略マネジメントツールとしてのBSC
前回BSCはKPIの測定ツールではなく、戦略マネジメントツールとして理解すべきであることをお伝えしました。この理解においてとても重要となるのが、以下の図です。

出典:「キャプランとノートンの戦略バランスト・スコアカード」ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、 櫻井通晴 著(東洋経済新報社、2001年)
この図に示すように 目標設定時には「財務」から「学習と成長」の方向に検討を進めるのですが、一方、その実現は、「学習と成長」から「財務」へと成果の連鎖があります。財務指標をゴールとして設定し、その実現のためにはどのような顧客価値を提示するのか、その新しい顧客価値の提供を実現するためには、特にどのビジネス・プロセスを競合他社に比してすぐれたものとする(「卓越」する)のかを定めます。
すなわち、バランスト・スコアカードを設計することは、自社なりの成功のシナリオを描くことに他なりません。
そして、全社のバランスト・スコアカードは最初に設計し、次いで事業部門→部・課→個人へとブレイクダウンさせ、個人や部門の業績評価を経営戦略とリンクさせるのです。
ここで重要になるのが、成功のシナリオを全社員が共有することで、その可視化ツールとして「戦略マップ」を作成します。
この戦略マップですが、我流で作成し、戦略の可視化・共有化ができていないことを良くみかけます。そのために、第2世代のバランスト・スコアカードでは、下記に示す、戦略マップのテンプレートが準備されました。

出典:「キャプランとノートンの戦略バランスト・スコアカード」ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、 櫻井通晴 著(東洋経済新報社、2001年)
顧客の視点に示されている顧客への3つの価値提案、「卓越した業務」、「顧客関係重視」、「製品リーダーシップ」、これがすなわち企業がとりうる戦略になります。財務の視点からたどると、企業の価値向上(米国式には株主価値の改善)のためには、収益増大と生産性向上の両方を考える必要がある。この収益増大のためには、新規および既存の顧客に何をアピールするのかを考えるのであるが、その選択肢が先に示した3つの戦略となる。3つを全て狙うのか、一つに絞るのかは上級経営者に求められる重大な意思決定となります。
さて、このテンプレートにおいて今一つ明確ではないのが、「学習と成長の視点」です。この4つめの視点について劇的な進化をさせ、IT投資との関係を明確にさせたのが、第3世代になります。次回はこの紹介をします。
BSCを正しく理解する その2 第2世代のBSC
第1世代のBSCは戦略実現に至る因果関係を説明するのに、4つの視点の事前的指標、事後的指標間の因果関係を定義しようとしました。以下にそのイメージを示します。MIT出身のキャプラン教授らしいアプローチですが、その為に戦略の全体像を把握することがほぼ不可能なものとなっていました。

第2世代のBSCはこの点を大いに反省し、「Strategy Focused Organization」という原題で出版されました。このタイトルが示しているように、第2世代からBSCは「戦略マネジメントツール」として位置付けられるようになります。
この本の出版と前後して、私はJISAのミッションで櫻井教授らとともに米国でのBSC導入成功企業を訪問しました。キャプランとノートンが作ったBalanced Scorecard Collaborativeにも訪問し、Harvardでは実際にキャプラン教授と意見交換する機会も持つことができました。
2001年のこのミッションのレポートは、以下で参照することができます。初心者だけでなくわかったつもりになっている方も一度目を通されることをお勧めします。
「バランスト・スコアカードによる戦略的経営の実践に関する調査研究」
第2世代のBSCについては、Balanced Scorecard Collaborative(現the Palladium)の訪問時に多くのサジェスションをもらい、上記の本でより理解を深めました。
なぜBSCを戦略マネジメントツールと呼ぶようになったのか、その理由は以下の通りです。
企業では戦略の展開のしにくさが問題となっており、戦略を実践できるように仕組みを作ることが最も重要である。実際、企業内に戦略を浸透させることを成功した企業は10%程度でしかない。このような企業の経営課題に対し、Balanced Scorecardのフレームワークは、戦略の実践における次の5つの障壁を克服しうるものである。
<戦略の実践における5つの障壁>
1.ビジョンの共有化での障壁
測定を通じて戦略の持つ意味を企業内に理解させ浸透させることができる。
2.コミュニケーション=人的な障壁
企業内での自分の位置付けを理解し、戦略の展開において、自分の役割を認識してもらうことができる。
3.経営資源の運用での障壁
経営資源(ヒト・モノ・かね)のどこに重点的に予算・計画を割り当て、戦略の展開に際しどこに投資すればよいかを決めることができる。
4.マネジメント面での障壁
戦略は継続的にフィードバックをかけその遂行方法を学習していかなければならないこと、長期的な視点で戦略を経営陣に認識させることができる。
5.リーダーシップ面での障壁
Balanced Scorecardを利用することで、経営陣は戦略を経営にあわせて軌道修正を加えることができる。
ここで、BSCは企業の戦略仮説を設定(可視化)するとともに、その進行状況をモニタリングし、戦略実現に向けて必要なアクションをとる、そのようなマネジメントツールとして再定義されたわけです。
そして、第2世代からBSCは、この戦略仮説を可視化するツールとして「戦略マップ」、その進行状況をモニタリングするツールとして「バランストスコアカード」の2つのセットとして説明されるように変りました。
次回は、戦略仮説の立案手順、モニタリング・軌道修正の方法について説明します。
BSCを正しく理解する
私がBSCに取り組みを始めたのは1998年ごろからで、その後2006年度から隔年で米国で開催されるBSCのExecutive Conferenceに参加しました。私が参加した回のテーマは下記の通りです。残念ながら各回とも日本人の参加者は私一人でした。
2007 Executive Conference
PUTTING YOUR PEOPLE WHERE YOUR STRATEGY IS
~Creating a High-Performance Organization
2008 Business Performance Conference
Measure, Monitor & Manage What Matters
Palladium’s Business Performance Conference 2010
Measures That Matter
2010年の段階でBSCは一旦成熟した状態になったので、その後は参加していませんが、それまでの10年間でBSCは大きく成長しました。
BSCはその発展段階に応じて3世代に分けることができ、それぞれ本が出版されています。
第1世代のBSC
私がバランスト・スコアカードに取り組み始めたのは、1998年度にJISA(社団法人情報サービス産業協会)の行政情報化委員会の部会長を務めてからです。この研究活動で、米国会計検査院(GAO)「エグゼクティブガイド~情報技術投資のパフォーマンス測定と成果の実証」(1997年9月)と米国国防総省(DOD)「投資としての情報技術(IT)管理とパフォーマンス測定についてのガイド」(1997年2月10日)を分析したのですが、その中でIT投資のパフォーマンス評価としてBSCを使うことが示されていました。
ただし、このガイドラインには次の2つの視点が含まれていて、すぐには理解しがたいところがありました。
- 導入する情報システムやネットワークについての評価
- 情報システム部門や情報化人材についての評価
そこで、特に1.の部分に特化して、当時専修大学の教授であった櫻井先生といっしょに、JISAの1999年度の事業で「バランスト・スコアカード活用による情報化投資評価の研究」というものに取り組みました。おそらく日本ではじめてBSCによるIT投資評価の実践方法をまとめたものだと思っています。
この時に参照したのが、BSCの第1世代の理論と事例をとりまとめた「吉川武男訳『バランスト・スコアカード』生産性出版、1997年」です。
第1世代のBSCでは、指標間(事前指標と事後指標)の関係性を定義していきますが、とても作成が困難でコンサルタントや戦略担当者の自己満足の道具となっていたのかもしれません。
このような反省から、第2世代のBSCが登場します。「キャプランとノートンの戦略バランスト・スコアカード」ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、 櫻井通晴 著(東洋経済新報社、2001年)がそれです。
この内容については次号で説明しますが、戦略マネジメントツールとしてのBSCの基本体系が第2世代では整理されます。
デジタルトランスフォーメーションの基礎となるBSC
日本のIT投資が守りになってしまうその奥深い理由としては、日本ではBSCの導入が進んでいないことがあげられます。
IT投資に限らずすべての投資は戦略を実現するためになされるべきなのですが、実はこの戦略マネジメントがうまくできていません。
日本の製造業のIoTが内部の改善にしか目が向けられていないという指摘をしましたが、その理由は、IoTで何を成し遂げたいかの戦略目標設定がなされておらず、IoTで何ができるかという、日本の企業やITベンダーが得意なシーズ志向の発想になっているからです。
効率化や品質改善への取り組みは日本企業のお家芸ともいえるもので、長らくその取り組みをしてきました。ですので、工場にIoTを入れて見えるかをしたとしてもその効果の及ぶ範囲は限定的で、あまり大きなリターンは期待できません。
ただ、この取り組みも、会社の戦略として、品質とリードタイムと価格で他社よりも抜きんでるということが設定されているのであれば、会社の方針とIoTの取り組みの整合が図れており、問題ありません。
しかしながら、例えば中小企業に目を向けてみると、彼らの第一の経営課題は効率化ではなく、売上の拡大です。その方法がわからず苦労しているところが多いのは事実ですが、品質とリードタイムと価格という従来からの強みでは生き残れないことは肌感覚でわかっています。そういう経営者にIoTで工場のラインの可視化をしましょうという話をしても、当然優先順位は低くなります。会社戦略とIT投資とが全く整合していないのです。
前回、生産機械メーカーさんとコマツさんの違いを書きましたが、その根本として、コマツさんは明確な戦略を打ち立てておられ、ソリューションを軸に市場シェアを獲得すると明言されています。ですので、外向きのIoTの活用ができているのです。
欧米の企業では当たり前のようにBSCが導入され、その結果、ビジネス戦略とIT投資との見事な整合が図れています。
したがって、世の中が急速にデジタル化するということへの対応するという経営課題が、IoTやオムニチャネルの優れた取り組みとして世の中にでてきているわけです。
そのため、次回は、BSCを使ってどのようにIT投資と戦略との整合を図るのかという点について、BSCの理解ということろからお話をしていきます。
IoTによる顧客価値創造をするには
前回日本製造業の多くが取り組んでいるIoTは、Industry 4.0と呼ばれるもので、これまでの改善のアプローチの延長線上でしなかいという指摘をしました。
一方、Industry4.0のトップランナーであるBoschは、2つのIoTをよく理解し、新たなビジネスリーダーの地位を築きつつあります。
既に述べましたように、特に製造業は、IoTのユーザでもありサービス提供者でもあるべきです。デジタルマニュファクチャリングなどという呼び方で、今は日本の製造業の多くは、製造ラインの生産機械をConnectedな状況にし、稼働時間、モータのトルク、駆動回数、電流、温度など様々なデータを取得し、「品質の更なる向上」と「生産性の向上」を図ろうとしています。このこと自体は、FAの時代からやってきたことですし、日本だけは普及していないMESというアプリケーションでもある程度実現できていたことです。
繰り返しますが、日本で今実施しているIoTは新しいことではなく、接続は面倒でしたが、世界ではある程度実現できていたことです。CPSにしても、Virtual Factoryというコンセプトで、5年前にはソリューションが出ていました。
では何が変ったのか、M2Mの技術標準が確立し、様々な機器、生産機械が接続しやすくなったので、一般化してきたということです。
さて、Boschは Industry 4.0に対して、「Dual strategy for connected strategy」として、Leading User, Leading Provider という戦略を提示しています。Leading Userとして積んだ経験をSolutionとして仕立てて他の製造業にサービスとして展開しています。彼らはこのソリューションを「 A machine and product-independent MES solution」としても位置付けており、MESユーザとしての深い経験がその基礎にあることを示しています。
日本の製造業はではなぜ、同様のアプローチがとれないのでしょうか?
生産機械のメーカであれば、自社内の工場でCPSを実現したのであれば、自社の生産機械のユーザーに対しても、同様の提案ができるのではないかと思いますが、どうもそのような発想にはならないようです。
その理由について、次回、日本での数少ない先行事例であるコマツのアプローチと生産機械メーカのアプローチを比較することによって、明らかにしていきたいと思います。
日本のIoTの課題 ~改善からの脱却
今、日本全国で都道府県、中小機構、商工会議所、職業訓練に関する教育施設などが盛んに中小企業のIoTへの取り組みを進めています。
事例集もいくつか公開されていますが、基本はセンサーで工場の機械の状況を把握できるようにしましょうというものです。
いわゆるIndustry4.0の流れです。
何度か引用していますが、Porter先生は、IoTの利活用は次の4つのレベルがあるとしています。
https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition

https://hbr.org/resources/images/article_assets/2014/10/R1411C_B.png
日本のIoTの取り組みの多くは、まだMonitoringのレベルで、これではデジタルトランスフォーメーションからは程遠い状況です。
デジタルトランスフォーメーションの基本は新しい顧客経験を提供することですが、日本のIoTの取り組みは改善にとどまっており、これを顧客経験に転換することができていません。
Industry4.0の代表例で良く紹介されるHarley-Davidsonでは、セルフデザイン、短納期という新たな顧客経験を提供し、顧客のロイヤリティ向上に大きく貢献しています。
日本での取り組みは、改善レベルであり、それを顧客にどう還元するのか、そのアイデアが出てきていません。
大きな課題が残っています。
デジタルトランスフォーメーションのゴールは?
前回、「デジタルトランスフォーメーションは経営課題である」という問題提起をしました。
Couchbase社が2017年5月に米国、英国、フランス、ドイツでデジタルトランスフォーメーションに積極的に取り組んでいる企業450社のCIOやCTOに実施したオンライン調査での「デジタルトランスフォーメーションのゴール」についての回答結果です。

出典:https://info.couchbase.com/2017_CIO_Survey_Report_LP.html
図に示す様に、特に「Very Important」というところで、顧客経験の改善が他の成果と比較して割合が抜きんでて多くなっています。
そこで、改めて、「顧客やエンドユーザに頃までとは異なる顧客経験を提供することが、デジタルトランスフォーメーションのゴールか」という問いをした結果が、次の図になります。

国によって若干の温度差はありますが、ほとんどの企業が、デジタルトランスフォーメーションの究極のゴールは、新たな顧客経験を提供することであると回答しています。
残念ながら、例えば経産省が中小企業に進めているIoTの推進施策はIndsustry4.0の視点、すなわち工場の可視化による生産性の向上という内向きの効果が中心になっているように、日本では「新たな顧客経験を提供する」という取り組みはとても弱いと言わざるを得ません。
いくら効率化してもそれを顧客価値に転換できなければ、その効果は極めて短命なものになってしまいます。
ただ、考えたくても、どのように取り組んでよいのかわからないというのが、本当のところだと思います。
それを考える方法論がサービスデザインであり、私がサービスデザインを日本にもっと普及させないといけないという強い危機感を持っている理由は、ここにあります。
デジタルトランスフォーメーションは経営課題!
デジタルトランスフォーメーションとは
日本でのデジタルトランスフォーメーションの定義は、以下のIDCのものが良く引用されています。
「企業が第3のプラットフォーム技術を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデル、新しい関係を通じて価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」
ここにある「第3のプラットフォーム」もIDCが提唱しているコンセプトで、「クラウド」「ビッグデータ」「モビリティ」「ソーシャル」の4要素によって形成される情報基盤のことだそうです。
これとよく似た概念はおそらく2013年頃からガートナーが「Nexus of Forces」というコンセプトを提案し、「クラウド」「モバイル」「ソーシャル」「インフォメーション」の4つがこれからの世の中を変えるとシンポジウムなどでプレゼンしていました。
当時はクラウドインテグレーションやSOAに取り組んでいましたので、全くピンとことなかったのですが、E-commerceやデジタルマーケティングを3年間経験した結果、納得できるようになりました。
ただ、おそらくほとんどの情報システム部門の人々は当時の私と同じ感覚を今も持っていると思います。それほど業務系システムとフロント系のシステムとは感覚が異なるものなのです。
本論に戻ります。
デジタルトランスフォーメーションの先駆者として良く例に出されているのが、UberやAirbnbです。彼らのビジネスモデルをみると、実にうまく第3のプラットフォームの4要素を使いこなしていることがわかります。
そこで、日本ではすぐにクラウドを使っていますかとかスマホをうまく取り入れていますがという議論、つまりプラットフォームを使えているかどうかの議論になってしまいます。これは大変なミスリードです。
怖いのは、かれらが既存市場を破壊してきていることです。Uberの登場によってタクシー会社は存立の危機に追い込まれています。これはAmazonがBordersやRadio Shackを倒産させた状況と似ています。
欧米の企業は他人事の様に考えていると、気づけば自分たちの市場がなくなっていたと、いうことが、ほんの数年のうちに起きてしまうという認識があるので、経営課題としてとらえられているわけです。
下記にそのことを示すデータがあります。

出典:https://info.couchbase.com/2017_CIO_Survey_Report_LP.html
同様の調査結果がMIT SLoanの調査でも出ているのですが、引用ができないので、こちらを紹介しています。デジタルトランスフォーメーションが自分たちの市場を破壊するという強い危機意識を持っていることがわかります。
それに比べて、日本の状況、皆さんの状況はいかがでしょうか?ITのことだと考えている人々があまりにも多いのではないでしょうか?
事実、国会図書館の雑誌記事索引で検索しても、100件も記事がなくしかも多くがIT関連の記事でした。
これに対して、HBR.ORGでデジタルトランスフォーメーションで検索すると1800件以上もの資料がありました。
この温度感の差は、大いなる危機です。
神戸でのサービスデザインワークショップ開催のご案内
9月16日、17日に神戸で開催されるサービスデザインのワークショップの開催のご案内をもらいました。
神戸市と、異人館の協力を得て実施するオープンなワークショップです。
https://www.facebook.com/events/113593789339246/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story&__mref=mb
開催時期が近いのですが、なかなか楽しそうなワークショップです。
私もアドバイザーとして参加したかったのですが、日本に不在なため、皆さんには是非参加頂きたく、ご案内します。
----------以下Facebookページより---------------------------------------
神戸と言えば、何をイメージしますか?
海やオシャレなお店、神戸牛などの美味しい料理など色々なことがあると思います。
その中の1つ神戸異人館が本イベントのテーマです。
明治時代に建設された異人館は1970年代から徐々に観光地化が進み、神戸を象徴する観光地になりました。
そんな歴史のある異人館だからこそ、課題や新しい楽しみ方を考える余地があります。
今回のイベントではサービスデザインという世界的に注目されている方法論を用いて神戸異人館のめぐり方や楽しみ方の新しいしくみを顧客視点から考えていただきます。
特別なスキルや経験がなくても参加できるイベントですので、ぜひご参加ください!
また、本イベントは9月16日(土)夜の宿泊費はイベント主催者側で負担致します。更に、学生には交通費も支給させていただきます。(ともに上限があります)
申込期限は9月5日ですが、定員に達し次第、締め切らせていただきますので、下記フォームからお早めにお申し込みください。
https://goo.gl/forms/SjMqq4K4yz4J1ALC2
【イベント概要】
日程:9月16日(土)13:00〜20:00
9月17日(日)9:30〜17:30
場所:神戸市異人館周辺エリア
主催:Code for Japan
パートナー:Google
参加人数:10〜15名程度
参加資格:2日間参加できる方
参加費:無料
特典:9/16(土)の無料宿泊、兵庫県外からの学生参加者には交通費支給(領収書をご持参ください)
申し込み:https://goo.gl/forms/SjMqq4K4yz4J1ALC2
問い合わせ先:jinnouchi{@}code4japan.org
本イベントはCode for Japan Summit
2017の一環として開催致します。
https://summit2017.code4japan.org/
【イベント詳細】
9/16(土)、9/17(日)の2日間に渡り、チームに分かれて現地でのインタビューやアイデア創出、動画撮影をおこなっていただきます。
インタビューや現地調査には異人館を運営されている、うろこの家グループ様に全面的にご協力いただきます。
また、プログラム期間中は専門家からのアドバイスを受けることができます。
<参加者イメージ>
・活動の範囲を拡げたいデザイナー
・まちづくりを学ぶ学生
・公共サービスを改善したい行政職員
・街と人の関係を考えたいプランナー
・UXデザインを学ぶ社会人
・企画力やプレゼン力を高めたいエンジニア
・サービスデザインに興味がある人 など
<スケジュール>
Day1.9/16(土)
オリエンテーション
現場調査とインタビュー
課題発見
コンセプトづくり
アイデアの発想
Day2.9/17(日)
カスタマー視点でのアイデアブラッシュアップ
プロトタイピング
シミュレーション動画撮影
終了後.
プレゼンテーション準備(動画編集/プレゼン資料作成)
Code for Japan
Summit前夜祭 9/22(金)
プレゼンテーション!
<サービスデザインとは?>
多様な分野が連携しあうことで、
顧客にとっての経験を強化し、
従業員の満足度を高め、
最新技術を活用しながら企業目標を追求し、
それらを通して事業の成功という
最終目標を目指す取り組み。
<サービスデザインのメリット>
・これまでにない新しいサービスが生まれやすい。
・多分野や多業種の連携を考えられるため、共創のアプローチが行いやすい。
・ニッチなニーズをもつ人にも対応できる。
・顧客視点で新しい体験を創出するため、「人」にやさしいソリューションが考えやすい
・顧客視点だけでなく、提供側の視点も同時に考慮するため、運用しやすくサスティナブルなアイデアが生まれやすい
入場無料
メーカーのオムニチャネル その2 これはゴールではない!
前回はパイロット店舗としてのメーカーの位置づけをご紹介しましたが、もう一つの考え方として、流通チャネルとターゲット顧客を分けるという方法もあります。
量販店と専門店では顧客層が異なるはずなので、メーカーの直営店やECサイトは量販店の顧客を奪わないように顧客層を設定し、そこに特化した販売を行うというものです。
オムニチャネルのキーワードとして、次は「パーソナライゼーション」であると前に記述しましたが、まさにそのアプローチを行うというものです。
ボリュームゾーンとは異なる商品を設定することで、一般商品では満足できない顧客層を掴むことを目的とします。
メーカーのどうしても克服できない課題として、最終消費者/購買者の情報を入手できないという壁があります。
これまでメーカーでは、商品開発に必要な情報を得るために、調査会社等による市場調査や、インターレストグループ、グループインタビューなどの消費者リサーチを行ってきましたが、これは消費者をマスでとらえる時にのみ有効な手段でした。
顧客の好みが多様化してきたため、この手法が通じなくなってきているのが事実で、消費者情報を知っているはずの量販店や専門店とのコラボを模索したり、ネットに明るい企業ではオウンドメディアによる顧客情報を収集しようとしています。
ただ、いずれも情報が偏っているというリスクがあります。量販店や専門店とのコラボではそれらの小売りが把握している顧客情報に頼ることになり、本当の顧客の姿は見えません。オウンドメディアでは、DMPを導入し3rdパーティーのデータを組み合わせることによってネット上でのプロファイルはある程度分析できるようになっていますが、それはあくまでもネット上での姿であってリアルでの顧客の姿とはなるものです。
さらにこれらの情報ではセグメント化はできますが、パーソナライズ化するには情報の質や粒度が不足しています。
メーカーでのオムニチャネルは、小売業のそれとは異なり、より深い顧客インサイトを得るためであると位置づけることが必要です。そうすることによって流通チャネルとの無用な軋轢をなくすことが可能になります。
前回のパイロット店舗と今回のスペシャリティチャネルはいずれかを選択するというものではなく、両方を併用することが大事です。
そして、大事なのは以前にも書きましたが、これはデジタルトランスフォーメーションの入り口にすぎないという認識を持つことです。副題の「これはゴールではない!」というのはそういう意味です。
次回からは、日本では大きく出遅れてしまっているデジタルトランスフォーメーションについて解説していきます。
メーカーのオムニチャネル その1
オムニチャネル適用の難易度は下記の順に難しくなっていきます。
- 直営店チェーン
- 日本の百貨店
- 直販を有するメーカー
何度か紹介しているMacy'sは基本全商品を自ら仕入れていますので、1.に相当しますが、日本の百貨店はフロア貸しが主ですので、在庫・商品コントロールができません。日本の百貨店でオムニチャネルが進まない理由はそこにあります。
大手スーパーチェーンなどは実行てきる環境があるはずなのですが、「快適な購買体験」=安さと品ぞろえと考えているため、オムニチャネルを導入することができないのです。
実際は先日紹介したインテルのビデオで指摘されていた様に、パーソナライゼーション能力を失ってしまっており、そこが「Friction Points」になっているのですが、気付けていないわけです。過去の成功体験に引きずられることの怖さがあります。
さて、今回は、これまで言及してこなかった3のケースについて考えていきたいと思います。直販ルート(ネット、リアル)を持つメーカーは多く、卸ルートと扱う商品を分けている場合はまだ良いのですが、重なっている場合は、流通さんとの競合がおきます。
一般にメーカーは消費者の情報が分からないと言われています。メーカーが直接取引しているのは、卸・商社、大型量販店であり、どのようなお客様が買っているのか、お客様が商品に対してどのような反応をしているかなどの情報を販売先は提供してくれず、そのためメーカーは知ることができません。
このためPOS情報を購入したり、アンテナショップを設けるなどして、何とか最終消費者のマーケティング情報を入手しようとしているわけです。
ところが、これはミレニアムの特徴だそうですが、メーカーと直接関係を持ちたいと考える消費者がでてきています。特に商品選択にあたって、専門的なサポートが必要な商品ではその傾向が強く、メーカー側もきちんと商品説明をしたいために、直接に消費者に販売したいと考えるようになり、直販ルートを持つメーカーが増えてきました。
その結果、同じ商品が卸ルートと直販ルートと両方で流れ、メーカー社内でも別々の事業部門が管轄しています。
この状況下で直販部門はお客様の利便性を高めるためにオムニチャネルにチャレンジしたいのですが、目立ちすぎると流通ルートと大きな摩擦を生むことになってしまうため、しっかりとした取り組みができず、中途半端なオムニチャネルがかえって顧客におおきなPoorな体験をさせてしまうことになります。
このジレンマに悩んでいるメーカーは多いのですが、きちんとしたサポートのできるベンダーは残念ながらないと考えて良いでしょう。
では、どうすれば良いのでしょうか。
メーカーは本来の立ち位置を再度思い出すことです。直販ルートが伸びるとはいえ、メインストリームにはならいないわけですから、直販ルートは、それを持つことによって得られた知見を流通ルートに還元することが目的であるということを再確認し、卸・商社、大型量販店がベンチマークできるような環境を提供することが求められているのではないでしょうか。
自分の店舗からの情報しか集まらい流通と、全国のデータが集まってくるメーカ。圧倒的な情報量の差がそこには存在しており、オムニチャネルを通じて得られた知見がそこに加われば、メーカーと流通の関係はかわるのではないでしょうか?
この具体的な内容は、次回に記載します。これもデジタルトランスフォーメションの一部になります。
サービスデザイン関西 第1回研究会開催報告
7/14 ナレッジサロンで第1回研究会開催しました。
当日のプログラムは下記です。
15:30~16:10
サービスデザインを如何に企業に定着させるか
㈱インフォバーン 京都支社長 井登友一さん
16:10~16:50
アジャイル開発とデザイン思考 DtoDの紹介
㈱オージス総研 アジャイル開発センター長 藤井 拓さん
16:50~17:05
Volkswagenにおけるサービスデザイン適用事例 SDGC2015より
Kyotoビジネスデザインラボ(同) 代表 宗平順己
17:05~17:25 全体質疑
終了後 6Fウメキタフロアに移動して懇親会
以下概要です。
1.サービスデザインを企業のメインストリームにするには?
・なぜサービスデザイン(SD)に抵抗があるのか?
今までと違うから自己否定への恐怖が根底にある
従来:作り手都合の開発のプロセス
↓
SD :ユーザー起点の開発プロセス
重要なこととして、ベテランを「間違った人にしない」こと。間違っていたわけではなくて、見方が違うだけであることを伝えること。彼らが納得すると強力な推進者に変わる。
<サービスデザインの見方>
・改善では良い製品/サービスにならない、過去の延長線上ではできない時代
・良い価値を良い文脈で届ける
Business とDesignの見方の違い
Business
顧客の声を聞く 全て要求を満たそうとすると結局使えないものになる
Design
本当は欲しかったものの気づきを与える
→ これでないと使わない という顧客を作ることができる
「利用者の隠れた動機・ゴール」をとらえると
顧客自身も意識していなかった経験 → 新しい価値(感動と習慣につながる)
=未来の当たり前をつくる
ユーザ中心からユーザ脱中心
抵抗その2 サービスデザインは時間がかかる
アプローチを変える
LEAN × ITERATION
Design Sprint
PrototypeとValidate=PDCA
具体的には次の講演へ。
Ⅱ.アジャイル要求開発
・サービスデザインででてきたアイデア それが妥当であるかを検証する
そこにアジャイル開発の価値がある
・残念ながらその検証をウォーターフォールで進めてしまうのが日本企業。
・欧米の所属が牽引して日本側もアジャイルに取り組む例が製造業が増えている
・以下の組合せで進めることが今後強く求められる
価値の定義:サービスデザイン
要求 :ユーザーストーリー、DtoD
開発手法:Scrum
DtoDについては下記を参照してください。
宗平注:
サービスデザインでサービスブループリントを作成し、そこからシステムに落とし込む際に、DtoDを適用するとシームレスにつなげることができそうです。これからの研究テーマにしますので、学会発表後こちらに掲載します。
3.Volkswagenにおけるサービスデザイン適用事例
ここでも一度取り上げました。
サービスデザインの教科書的お手本ともいえるアプローチとしてVWのビジネスイノベーションチームの取り組み例をご紹介しました。
「The privacy vs. convenience dilemma of “PaketAuto”,A service design challenge, Daniel Canis, SDGCC2015」
終了後はウメキタフロアに移って、持ち寄りパーティーを開催しました。話が尽きることなく、有意義な時間を過ごすことになりました。
この研究会組織はサイボウズライブ上にコミュニティを作成します。
次回のオフ会は11月下旬、SDGC2017の参加報告の予定です。
デジタルトランスフォーメンション?
前回までのデジタル・リテール、これまでご紹介してきたIoTやオムニチャネルなどのイノベーションは、「デジタルトランスフォーメション」と総称されます。
この「「デジタルトランスフォーメション」ですが、Wikipediaをみるとまず最初に以下の様に記述されています。
デジタルトランスフォーメーション(Digital transformation)とは、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念である。2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱したとされる。
ちょっと何か違和感がありますね。
一方市場調査会社のIDCは以下の様に定義しています。
「企業が第3のプラットフォーム技術を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデル、新しい関係を通じて価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」
冒頭の「第3のプラットフォーム」という言葉ですが、2014のITproまとめに既に解説が掲載されていました。
そのまま引用します。
出典:http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20140226/539724/?rt=nocnt
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第3のプラットフォーム(3rd Platform)とは、調査会社の米IDCが提唱しているコンセプトで、「クラウド」「ビッグデータ」「モビリティ」「ソーシャル」の4要素によって形成される情報基盤のこと。なお、第1のプラットフォームはメインフレーム、第2のプラットフォームはクライアント/サーバーを指す。
同様の概念として、米ガートナーは「Nexus of Forces」(力の結節)を提唱する。Nexus of Forcesでは、「クラウド」「モバイル」「ソーシャル」「インフォメーション」の4つを挙げるが、このインフォメーションとは、すなわちビッグデータのことだ。
このほかにも、ソーシャル(Social)、モバイル(Mobile)、ビッグデータを呼び換えたアナリシス(Analysis)、クラウド(Cloud)の頭文字を取ってSMACと呼ぶこともある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このうちビッグデータについてはAIに置き換えられつつあると考えて良いでしょうね。
さて、大事なのは世の中に、クラウド、ソーシャル、スマホ、AIといった環境が整ってきている、これを好機と捉えて、「新しい価値を創出する」ことです。
デジタルトランスフォーメーションの先駆者として良く例に出されているのが、UberやAirbnbです。彼らのビジネスモデルをみると、実にうまく第3のプラットフォームの4要素を使いこなしていることがわかります。
そのことについて、うまいこと使っとる、よー考えとると他人事でいててはいけません。怖いのは、かれらが既存市場を破壊してきていることです。他人事の様に考えていると、気づけば自分たちの市場がなくなっていたということが、ほんの数年のうちに起きてしまいます。そこを肝に銘ずるべきです。
我々はこれまで「しくみ」にとらわれてきて、その部分をアピールすることに慣れてきてしまっています。しかしながら、第3のプラットフォームの登場により、しくみは誰でも使えるものになり、そこでの優位性を担保することが不可能になってきています。
そこで今競争優位の鍵となるのが、「顧客価値」であるわけです。そして、その最も重要な切り口が「顧客起点で物事を考えこと」、すなわち、サービスデザインのアプローチであるわけです。
ということで、このブログの初回にまた話題が戻ってきました。